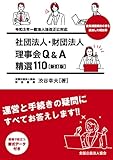公益社団法人と一般社団法人の違い
公益社団法人の設立要件と認定基準
公益社団法人は、一般社団法人として設立した後に行政庁(内閣府または都道府県)から公益認定を受けることで成立します。公益認定を受けるためには、公益認定法第5条に定められた21項目の厳格な基準をすべて満たす必要があります。主な認定基準として、公益目的事業を主たる目的とすること、経理的基礎と技術的能力を有すること、社員や役員に特別の利益を与えないこと、公益目的事業比率が50%以上であることなどが挙げられます。
参考)https://www.syadan-npo.com/cat-5/213.html
公益目的事業とは、学術・科学技術の振興、文化・芸術の振興、高齢者の福祉増進、地域社会の健全な発展、公衆衛生の向上など、認定法に基づく23種類の事業に限定されています。これらの事業は社会全般の不特定多数の利益増進に貢献するものでなければなりません。設立期間は一般社団法人の設立に2~4週間かかり、さらに公益認定の審査期間が加わります。
参考)https://www.koueki-houjin.net/shadan/tigai.html
公益社団法人の組織体制には、理事3名以上、監事1名以上が必要で、理事会の設置が必須となります。理論上は4名での構成が可能ですが、社員と理事の兼任、代表理事の選定など、法定要件を満たす必要があります。ただし、4名体制では意思決定の停滞や業務負担の集中などのリスクがあるため、実際には余裕を持った人員配置が推奨されています。
参考)https://www.koueki.jp/blog/requirement-headcount/
一般社団法人の設立手続きと組織構成
一般社団法人は、2名以上の社員がいれば法務局への登記のみで簡単に設立できる法人形態です。主務官庁の許可を必要とせず、公益性も求められないため、公序良俗に反しない限りどのような事業でも自由に行うことができます。株式会社のように収益事業のみを目的として設立することも可能で、各種学会、協会、同窓会、町内会、互助会などの任意団体を法人化するのに適しています。
設立時の費用として、公証人手数料50,000円と登録免許税60,000円が必要です。設立期間は2週間から4週間程度で、所轄庁や監督機関は存在せず、基本的に自由な事業運営が認められています。
組織構成については、社員で構成する社員総会と理事を必ず置く必要があります。理事は1名以上いれば問題なく、社員と理事は兼任できるため、延べ人数2名で一般社団法人を設立することが可能です。定款の定めによって、理事会、監事、会計監査人を任意で設置できます。理事会を設置する場合は、理事3名以上、監事1名以上が必要となり、組織の規模に応じて5パターンの機関設計が可能です。
参考)https://www.koueki-houjin.net/shadan/
公益社団法人と一般社団法人の税制上の違い
公益社団法人と一般社団法人では、税制上の取り扱いに大きな違いがあります。公益社団法人の法人税は原則非課税であり、公益目的事業として認定された事業は収益事業に該当する場合でも非課税となります。一方、一般社団法人は全所得課税と収益事業課税に区分され、税率は会社と同じです。
参考)https://biz.service.ntt-east.co.jp/columns/shadan/
公益社団法人には、寄付金優遇税制が適用されます。個人が一定の条件を満たした公益法人に寄附した場合、その年中の寄附金から2,000円を控除した金額の40%相当額を、所得税の額から控除できます(所得税の25%相当額を限度)。この適用を受けるためには、実績判定期間において、年間3,000円以上寄付した個人・法人が平均100人以上いること、または年間収入に占める寄附金等収入の比率が5分の1以上であることのいずれかを満たす必要があります。
参考)https://kohokyo.or.jp/jaco40/sector/taxation/detail/
一般社団法人でも、非営利型の場合は寄付金優遇が適用されます。しかし、公益社団法人のような包括的な税制優遇は受けられません。公益社団法人は毎年度、行政庁への報告が義務付けられており、公益認定の基準を満たせなくなると認定を取り消されるリスクがあります。
参考)https://www.agsc.co.jp/ags-media/public-interest-corporation/
建築業界における一般社団法人の活用事例
建築業界では、公益法人改革に伴い、多くの業界団体が一般社団法人への移行を選択しています。建築業協会(BCS)、日本道路建設業協会(道建協)、日本建設業経営協会(日建経)、海外建設協会(海建協)などは、一般社団法人化を視野に入れた検討を進め、2011年度中に移行申請を行いました。日本建設業団体連合会(日建連)も一般社団法人を選択する方向で調整を進めました。
参考)https://www.to-you-lawyer.com/%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%80%81%E3%80%8C%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%A4%BE%E5%9B%A3%E3%80%8D%E3%81%8C%E5%A4%9A%E6%95%B0%E6%B4%BE%E3%81%AB-%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E5%B7%A5%E6%A5%AD
一般社団法人を選択する背景には、公益社団法人の認定や維持の難しさがあります。公益社団法人では公益目的事業の比率を50%以上とすることが求められ、会員企業向けの共益事業がやりにくくなるといった懸念があるためです。一般社団法人化により、これまでの規制がなくなり、創意工夫による自由な事業選択が可能になります。
参考)https://www.token.or.jp/news/news20130401_01.html
東京建設業協会は2013年4月に一般社団法人へ移行し、会員メリットの向上と社会貢献的活動の両立を目指しています。具体的には、建設業の継続性、防災・減災、発災時の対応体制の整備を重点事業として取り組んでいます。また、一般財団法人や一般社団法人も建設業許可を取得でき、公益的・共益的事業はもちろん、収益事業を行うことも可能です。
参考)https://www.sugawara4976.com/inform/%E4%B8%80%E8%88%AC%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF/
公益社団法人と一般社団法人の選択基準と注意点
公益社団法人と一般社団法人のどちらを選択するかは、事業の目的、運営方針、税制上のメリット、維持管理のコストなどを総合的に判断する必要があります。公益社団法人は高い社会的信用を得られ、法人税の軽減や寄付金優遇税制などのメリットがありますが、厳格なガバナンスが求められ、事業費の半分以上を公益目的事業に充てなければなりません。
一般社団法人は設立が容易で、事業目的の自由度が高く、営利・非営利にかかわらず比較的自由な事業運営が認められています。監督機関もないため、柔軟な運営が可能です。ただし、社会的信用は公益社団法人に比べて低く、全所得課税または収益事業課税の対象となります。
公益社団法人になるためには、高度な専門知識が必要で、公益法人制度に精通した専門家の支援が不可欠です。公益認定を前提とした定款の作成や事業計画の策定、特殊な税務会計の処理など、難易度が非常に高くなります。一般社団法人から公益社団法人への移行は可能ですが、公益認定等委員会による審査を受け、所定の基準を満たしていると認められる必要があります。
また、一般社団法人も一般財団法人も、株式会社とは異なり剰余金の分配はできないため注意が必要です。建築業従事者が法人化を検討する際には、事業の性質、規模、将来の展望を踏まえ、最適な法人形態を選択することが重要です。
<参考リンク>
公益社団法人と一般社団法人の設立要件・組織構成・税制の詳細な比較表が掲載されています。
一般社団法人と公益社団法人の違い - 一般社団法人設立支援センター
建築業界団体が一般社団法人を選択した背景と理由について詳しく解説されています。
建設業団体、「一般社団」が多数派に - 建設工業新聞
公益認定の21項目の基準について詳細に説明されています。
公益認定の基準 - じぶんでできる公益法人設立
一般社団法人の組織構成と機関設計の5パターンについて解説されています。