

メタルラス 種類と特徴
メタルラス 種類の基本と分類方法
メタルラスは建築現場において左官工事の下地材として重要な役割を果たしています。JIS A 5505の規格に基づき、メタルラスは大きく分けて「平ラス」「こぶラス」「波形ラス」「リブラス」の4種類に分類されています。これらは形状や用途によって区別され、それぞれ特有の特徴を持っています。
メタルラスの基本構造は、薄い鋼板(板厚0.3mm~1.0mm)に切れ目を入れ、引き伸ばして網状にしたものです。この製造方法により、一枚の板から作られるため網目がもつれたりほどけたりすることがなく、強固な下地材となります。
材質については、主に以下の3種類が使用されています。
2014年8月にJIS規格が改定され、メッシュサイズがⅠ型(R26×S13mm)とⅡ型(R32×S16mm)の2つに区分されるようになりました。また、製品寸法も幅600~1000mm×長さ1800~2000mmの範囲に拡大されています。
平ラスとこぶラスの特徴と左官工事での使い方
平ラス(略号F:フラット)は、成型などの二次加工がされていない平らなメタルラスです。最も基本的な形状で、主に内装用として使用されます。JIS規格では質量によってF450(旧1号品)、F500(旧2号品)、F700(旧3号品)、F1050(旧4号品)に分類されています。
平ラスの特徴。
- シンプルな構造で扱いやすい
- 耐火性や耐震性に優れている
- 壁面以外にも天井などにも利用可能
- 住宅の外壁には使用できない(内装用)
こぶラス(略号K:こぶ)は、平ラスを同一方向にこぶ付け加工したメタルラスです。2014年のJIS規格改定により、m²質量800gの製品に限定され、山高9mmと11mmの2種類となりました。また、こぶピッチも157×167mmと広くなっています。
こぶラスの特徴。
- こぶ(突起)によりモルタルとの密着性が向上
- モルタルの厚みを均一に保ちやすい
- 平ラスよりも強度が高い
施工時の注意点として、メタルラスの塗り厚が薄くなると空気に触れる面積が多くなり、錆が発生するリスクがあります。錆びるとモルタルや壁土が剥がれ落ちる原因となるため、適切な塗り厚を確保することが重要です。
波形ラスとリブラスの構造と鉄骨造での活用方法
波形ラス(略号W:ウエーブ)は、平ラスを一定方向に波付け加工したメタルラスです。主に外壁に使用され、断面が波の形状をしていることで下地との剥離が少ないという特徴があります。
波形ラスの種類と特徴。
- 山高によってW700-06(6mm)、W700-08(8mm)、W700-10(10mm)などに分類
- 質量も700g/m²と1050g/m²の2種類がある
- 波形の構造により、モルタルとの密着性が高い
- 外壁用途に適している
リブラス(略号R:リブ)は、メッシュの間に一定間隔でリブと呼ばれる帯状に成形された骨部が配置されたラスです。主に鉄骨造の建築物で使用され、製造方法によりリブラスAとリブラスCの2タイプに区分されます。
リブラスの特徴。
- リブ(骨部)により強度が高い
- 鉄骨造建築物に適している
- 住宅で通気工法をする際にも使用される
- リブラスAは形状が同じでも原板の厚さにより質量が異なる種類がある
- リブの形状はV型が一般的
鉄骨造建築物では、リブラスが特に重要な役割を果たします。リブ構造により、モルタルとの密着性が高まり、壁面の強度を確保できます。また、通気工法を採用する住宅建築においても、リブラスは効果的な下地材となります。
メタルラス 種類ごとのJIS規格と品質基準
メタルラスの品質はJIS A 5505の規格によって厳格に管理されています。この規格では、メタルラスの形状、寸法、質量、外観などについて詳細に規定されています。
JIS規格における外観の要件。
- 形状が正しく、目切れがなく、かつ有害なさびがないこと
- 刻み幅が斉一(均一)であること
2014年の規格改定により、以下のような変更が行われました。
- 使用材料に溶融亜鉛めっき鋼板及びステンレス鋼板が追加
- メッシュサイズの区分が明確化(Ⅰ型とⅡ型)
- 製品寸法の範囲拡大
- 号表記の廃止と、製品のメッシュ区分・m²質量・山の高さ・素材及びめっき付着量表示への変更
製品の呼び方も変更され、例えば平ラスの場合「Ⅱ F 450(1号)Z 12」のように表記されるようになりました。これはメッシュ寸法記号、種類の記号、単位面積当たりの質量、旧呼び方、材料記号及び表面処理記号、JIS G3302のめっき付着量を表しています。
各種ラスの寸法、質量、許容差についても詳細に規定されており、例えば平ラスの場合、単位面積当たりの質量は450g/m²~1050g/m²の範囲で、許容差は±14g~±32gとなっています。
メタルラス 種類と他のラス下地材との比較分析
建築現場では、メタルラス以外にも様々なラス下地材が使用されています。それぞれの特性を理解し、適切に選択することが重要です。
ワイヤーラスとの比較。
ワイヤーラスは針金を編んで作成した金網状のラスで、メタルラスとは製造方法が異なります。メタルラスが薄い鉄板を引き延ばしたものであるのに対し、ワイヤーラスは針金を網目状に編んだものです。
主な違い。
- 厚み:ワイヤーラスの方が厚みがある
- 塗り厚:ワイヤーラスの方が塗り厚が大きくなる
- 編み方:ひし形ラス、亀甲形ラス、丸形ラスの3種類がある
ラスカットとの比較。
ラスカットは合板にモルタルが塗装された製品で、壁に貼り付けるだけで左官工事の下地として使用できます。
ラスカットの特徴。
- 工程の省略化が可能
- 工期短縮につながる
- 価格は高いが、工期短縮による工費削減で全体のコスト削減が可能
メタルラスの選定基準。
- 用途(内装・外装)
- 建築構造(木造・鉄骨造など)
- 必要な強度
- 施工方法(通気工法など)
- 予算
適切なラス下地材の選択は、建築物の品質や耐久性に直接影響します。特に左官工事においては、仕様書に記載された内容に基づいて適切なラス下地を選択することが重要です。間違ったラスの使用や接合方法の誤りは、塗装したモルタルや壁土が剥がれ落ちる原因となります。
メタルラス 種類別の施工テクニックと防錆対策
メタルラスを使用した施工では、種類ごとに適切な施工テクニックを用いることが重要です。また、メタルラスの最大の弱点である錆の発生を防ぐための対策も必要です。
施工時の基本ポイント。
- 下地の清掃と平滑化
- メタルラスの適切な固定(釘やステープルの間隔に注意)
- ラス同士の重ね代の確保(一般的に50mm以上)
- コーナー部分の補強
- 適切な塗り厚の確保
種類別の施工テクニック。
平ラス。
- 内装用途が主であるため、湿気の少ない環境での使用が基本
- 釘やステープルで確実に固定し、浮きがないようにする
- 塗り厚は最低でも10mm以上確保する
こぶラス。
- こぶの高さを考慮した塗り厚を確保する
- こぶの向きを統一して施工する
- 下地との間に適切な空間を確保する
波形ラス。
- 波の方向を考慮して施工する(通常は垂直方向)
- 波の谷部分にもモルタルが十分に入り込むよう注意する
- 外壁用途が多いため、防水対策と組み合わせて施工する
リブラス。
- リブの向きを考慮して施工する
- 鉄骨下地への固定方法に注意(溶接や専用金具を使用)
- 通気工法の場合は通気層の確保に注意する
防錆対策。
- 適切な塗り厚の確保(最低でも10mm以上)
- 高品質な防錆処理済みメタルラスの使用
- 施工前の保管状態に注意(湿気の多い場所での保管を避ける)
- 施工後の早期モルタル塗り(メタルラス施工後は速やかにモルタル塗りを行う)
- 防水層との適切な組み合わせ
特に外壁に使用する波形ラスやリブラスでは、防水対策と組み合わせた施工が重要です。防水シートとの組み合わせや、適切な通気層の確保により、メタルラスの寿命を延ばし、建築物の耐久性を高めることができます。
また、近年では溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板を使用した高耐食性のメタルラスも開発されており、従来の溶融亜鉛めっき鋼板に比べて防錆性能が大幅に向上しています。建築物の長寿命化を考慮する場合は、こうした高性能なメタルラスの使用も検討する価値があります。
メタルラスの施工品質は、建築物の耐久性に直接影響します。特に塗り厚が不足すると、メタルラスが空気に触れる面積が増え、錆の発生リスクが高まります。施工時には、適切な塗り厚を確保し、メタルラスが完全にモルタルに埋め込まれるよう注意することが重要です。
メタルラス 種類の最新トレンドと環境配慮型製品
建築業界では、環境への配慮や施工効率の向上を目指した新しいメタルラス製品が開発されています。最新のトレンドと環境配慮型製品について見ていきましょう。
最新のメタルラストレンド。
- 高耐食性メタルラス
溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(ZAM)を使用したメタルラスが増加しています。従来の溶融亜鉛めっき鋼板に比べて、耐食性が2~5倍向上し、建築物の長寿命化に貢献します。
- 軽量高強度メタルラス
従来品よりも軽量でありながら、強度を維持した製品が開発されています。施工時の負担軽減や、建築物の軽量化に貢献します。
- 複合機能型メタルラス
防火性能や断熱性能を高めた複合機能型のメタルラスも登場しています。例えば、断熱材と一体化したメタルラスは、施工効率の向上と断熱性能の確保を同時に実現します。
環境配慮型メタルラス製品。
- リサイクル材料使用製品
鉄スクラップなどのリサイクル材料を原料とした環境負荷の少ないメタルラスが開発されています。
- 長寿命化製品
高耐食性を持つメタルラスは、建築物の長寿命化に貢献し、結果的に廃棄物削減につながります。
- VOC(揮発性有機化合物)フリーコーティング
一部のメタルラス製品では、環境や人体に悪影響を与えるVOCを含まないコーティングが施されています。
施工効率を高める新製品。
- 大判サイズ製品
従来よりも大きなサイズのメタルラスが開発され、施工効率の向上に貢献しています。
- 専用固定金具との組み合わせ
メタルラスの固定を容易にする専用金具と組み合わせた製品も登場し、施工時間の短縮が可能になっています。
- プレカット製品
建築現場での加工を最小限に抑えるプレカット製品も増えており、施工精度の向上と廃材削減に貢献しています。
これらの新しいメタルラス製品は、従来品に比べて価格は高くなる傾向がありますが、施工効率の向上や建築物の長寿命化によるライフサイクルコストの削減が期待できます。特に環境配慮が求められる公共建築物や長期使用を前提とした高品質な建築物では、こうした高機能メタルラスの採用が増えています。
建築施工従事者としては、これらの最新製品の特性や施工方法を理解し、適材適所で活用することが重要です。また、発注者に対しても、初期コストだけでなくライフサイクルコストや環境負荷の観点からメタルラスを選定することの重要性を説明できるようになることが求められています。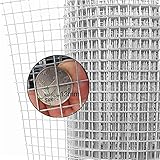
金網 メッシュ 金網柵 ステンレス鋼 オーチャードフェンス 1x5m 1x10m 防錆 金属メッシュフェンス チキンワイヤーメッシュ ネズミ侵入防止 家禽網 網戸メッシュ 溶接メッシュ 防鼠金網 産業用金網 (Size : 1x1m)

