

アルミ板の規格
アルミ板規格の基本体系と材質分類
アルミ板の規格はJIS H4000に基づいて厳格に定められており、建築業界では主にA1050、A1100、A5052の3つの材質が使用されています。A1050は純度99.5%以上の高純度アルミニウムで、優れた耐食性と成形性を持ちます。A1100は純度99%以上で、A1050より若干強度が高く、最もコストパフォーマンスに優れています。
最も建築業界で重宝されているのはA5052で、Al-Mg系合金として中程度の強度を持ち、耐食性、成形性、溶接性のバランスが優秀です。この材質は船舶や車両、建築用材として幅広く採用されており、一般的に「52S」と呼ばれています。
調質状態では、H14(硬質)とH24(半硬質)が主流で、用途に応じて選択します。H14は強度が高く構造材向け、H24は加工性が良好で成形加工が必要な部材に適しています。
アルミ板規格の標準寸法と板厚体系
標準的な規格寸法として、最も一般的な1000×2000mmをはじめ、1250×2500mm、1250×3000mm、1525×3050mmが定番サイズとして流通しています。海外規格の4'×8'(1219×2438mm)や5'×10'(1525×3050mm)も建築現場では頻繁に使用されます。
板厚規格は0.3mmから350mmまで非常に幅広く対応しており、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10mmが標準板厚として常時在庫されています。特に建築用途では1.0mm~3.0mmの範囲が最も使用頻度が高くなります。
極厚板では15mm以上の厚板も規格化されており、構造部材や機械加工用として50mm、100mm、さらには200mmを超える厚板まで対応可能です。重量計算では比重2.7を用いて、寸法×板厚×2.7で1枚あたりの重量を算出します。
アルミ板規格における表面処理と品質基準
アルミ板の表面処理規格では、生地材(無処理)が最も基本的で、コストを重視する建築用途に適しています。シルバーアルマイト処理(B2)は耐食性と美観性を向上させ、建築外装材として人気があります。
品質基準では切断精度が重要で、シャーリング切断では±3.0mm、レーザーカットでは±0.1mm程度の精度が確保されています。保護シートは片面または両面に貼付されており、輸送・保管時の傷防止に配慮されています。
JIS規格相当品として輸入材も流通していますが、品質管理の観点から国産材の使用が推奨されます。特に建築基準法に関わる構造材では、JIS認定品の使用が必須となる場合があります。
縞板(チェッカープレート)も重要な規格品で、滑り止め効果を持つ床材として2.0mm~4.5mmの板厚で標準化されています。パターンAとパターンBの2種類があり、用途に応じて選択可能です。
アルミ板規格選定時の実用的判断基準
建築プロジェクトにおけるアルミ板選定では、まず荷重計算から必要板厚を決定します。軽量化を重視する場合はA5052の1.5mm~2.0mmが最適で、強度が必要な構造部材では3.0mm以上を選択します。
コストパフォーマンスを重視する場合、定尺サイズ(1000×2000mm)の活用が効果的で、オーダーカットよりも20~30%程度のコスト削減が可能です。在庫回転の早い標準板厚を選ぶことで、リードタイム短縮も実現できます。
加工性を考慮する際、曲げ加工が必要な場合はH24調質、溶接を伴う場合はA5052材質を選択することで、作業効率が大幅に向上します。レーザーカットやウォータージェットカットを予定している場合は、板厚と材質の組み合わせで切断速度が変わるため、加工業者との事前確認が重要です。
アルミ板規格の将来展望と新技術対応
建築業界では環境配慮型材料への転換が進んでおり、リサイクル可能なアルミニウム合金への注目が高まっています。新しい合金開発では、従来のA5052を上回る強度と加工性を両立した6000系合金が建築用途でも採用され始めています。
デジタル技術の活用により、BIM(Building Information Modeling)と連動した材料選定システムが導入されており、3Dモデルから直接必要な板厚や寸法を算出し、最適な規格品を自動選択する仕組みが普及しています。この技術により、材料ロスを10~15%削減できる事例が報告されています。
また、オンデマンド生産システムの発達により、従来の定尺サイズに加えて、プロジェクト専用サイズでの効率的な調達が可能になっています。AI を活用した需要予測により、建築業界特有の季節変動にも柔軟に対応できる供給体制が構築されています。
プレハブ建築や仮設構造物では、アルミニウム合金の軽量性を活かした新しい接合技術が開発されており、ボルト接合に加えて機械的嵌合システムが実用化段階に入っています。これらの技術により、組立時間の短縮と解体時のリサイクル性向上が同時に実現されています。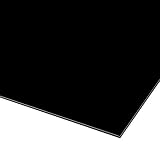
アルミ複合板 ブラック (両面つや無) カラーエース 厚み3mm 600×900mm ★縮小カット1枚無料★ (受注生産品キャンセル・返品不可、メーカー規格板は法人限定出品に移行しました)

