

JIS規格電気設備技術基準解釈
JIS規格電気設備における技術基準解釈の基本概要
JIS規格電気設備の技術基準は、電気設備の安全な設計、工事、運転を確保するための重要な指針です。電気設備の技術基準の解釈では、電気使用場所における電気設備が設置される場所の定義が明確に規定されており、屋内の場合はその建物を一つの電気使用場所として扱います。
電気設備の技術基準解釈において、使用電圧の定義は電気学会電気規格調査会標準規格JEC-0222-2009に基づいて定められており、公称電圧が1,000Vを超える電線路では3,300Vから1,000,000Vまでの標準電圧が設定されています。また、公称電圧が1,000V以下の電線路では100V、200V、100/200V、230V、400V、230/400Vの公称電圧が標準として定められています。
最大使用電圧は事故時の異常電圧ではなく、通常の運転状態でその回路に加わる線間電圧の最大値を指し、軽負荷運転や無負荷運転時の電圧変動を考慮に入れて決定されます。この基準により、電気設備の安全性と信頼性が確保されています。
さらに、電気設備には標高による使用環境の規定があり、直流電源装置や無停電電源装置(UPS)は標高1,000m以下の使用環境で設計されています。これは高標高地域における空気密度の低下による冷却効率の低下や絶縁性能の変化を考慮した安全対策です。
JIS規格電気設備における特殊設備対応要求事項の詳細
JIS規格電気設備では、特殊設備や特殊場所に対する個別の要求事項が詳細に規定されています。JIS C 0364規格群は、低圧電気設備の安全保護、選定及び施工、並びに検証について規定する個別製品規格として、特殊設備又は特殊場所に関する要求事項を定めています。
2024年2月20日にはJIS C 0364-7-714:2024(屋外照明設備)とJIS C 0364-7-722:2024(電気自動車用電源)が発行されました。これらの改正・制定により、国際規格との整合が図られ、海外製品の輸入の可能性が広がるなど、国際取引の円滑化が期待されています。
屋外照明設備に関する改正では、照明器具及び照明設備の範囲が拡大され、選定及び施工の確実性が向上しました。一方、電気自動車用電源に関する新規制定により、電気自動車用電源の施工者の安全性に対する要求事項が明確になっています。
医用電気設備においても、JIS規格「病院電気設備の安全基準」により、医療機器・医療設備への電源の供給信頼性の確保と、患者と操作者の電気的安全確保のため、一般の建物より厳しい要求事項が設定されています。生命維持装置には0.5秒以内の電力供給が必要であり、瞬時特別非常電源(交流無停電電源装置を含む)の設置が義務付けられています。
JIS規格電気設備における熱的強度確認方法と適合性評価
電気機械器具の熱的強度については、電気設備の技術基準の解釈に具体的な規定はありませんが、電気規格調査会標準規格による確認方法が確立されています。変圧器、開閉器類などの電気機械器具には、それぞれ個別の熱的強度関係の規格が適用されます。
変圧器については「変圧器」JEC-2200、「配電用6kV油入変圧器」JIS C 4304、「配電用6kVモールド変圧器」JIS C 4306が適用されます。開閉器類には「交流遮断器」JEC-2300、「交流断路器および接地開閉器」JEC-2310、「電力ヒューズ」JEC-2330などの規格が適用されています。
これらの熱的強度確認は、電気機械器具の安全性と信頼性を確保するために重要であり、適切な試験と評価により機器の性能が保証されます。特に高温環境や連続運転条件下での安全性確保には、厳密な熱的強度評価が不可欠です。
公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)では、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として制定されており、JIS規格との整合性を図りながら実際の施工における指針を提供しています。
JIS規格電気設備における国際規格対応と技術的課題
JIS規格電気設備は、国際電気技術委員会(IEC)規格との整合を図りながら発展してきました。IEC 60364規格群との対応により、日本の電気設備技術基準は国際的な技術水準に適合しています。しかし、規格の実装においては製造業者間での解釈の違いが生じることもあります。
スマートグリッド通信における標準化では、IEC 61850通信プロトコルが変電所自動化システムにおいて重要な役割を果たしています。このプロトコルは、計器用変成器、遮断器、電力変圧器などの高電圧一次設備と各種インテリジェント電子機器との一貫した通信と統合を確保するために定義されています。
電気自動車の普及に伴い、電気推進車両の標準化環境も複雑化しており、水素などの新エネルギーベクトルを考慮すると、関連する標準化環境はさらに複雑になっています。ハイブリッド電気駆動技術の展開への関心の高まりにより、特定の標準化問題が発生しており、専門の技術チームがこれらの課題に取り組んでいます。
IEC 61000-3-2およびIEC 61000-3-12規格の要求事項評価では、広帯域電流変換器の適用における変換精度の確認が重要な課題となっています。50Hzの主周波数および100Hzから2,500Hzの高調波周波数範囲での歪み電流に対する振幅誤差と位相シフトの評価が必要です。
JIS規格電気設備における意外な技術動向と将来展望
JIS規格電気設備の分野では、一般的にはあまり知られていない興味深い技術動向があります。フォトルミネッセンス(PL)法による半導体結晶の不純物定量分析技術がJIS規格として確立されており、JIS HO615として1996年に登録されました。この技術は、シリコン結晶中の極微量不純物(原子比0.1ppb以下)を高精度で検出できる画期的な手法です。
シリコン半導体は間接遷移型のため発光効率が低く、発光波長も近赤外領域で測定が困難でしたが、特定の実験条件下でPL解析による不純物定量分析が可能となりました。この技術の標準化により、JEIDA-45規格、ASTM F1389-92規格との国際的な連携も実現されています。
電気設備の技術基準解釈では、2024年10月22日に高圧1,500V以下での運用に関する海外規格との整合を図る改正が行われました。この改正により、電気設備の技術基準省令や電技解釈の関係条文を参考にした想定リスク調査に基づき、保安要件の追加が決定されています。
日本のエネルギー効率基準プログラムは、市場で最高のエネルギー効率を持つ製品に基づいて義務的な基準を設定・改定するユニークなプログラムです。エアコンを対象とした分析では、1999年から2040年までの期間において、割引率3%を適用した場合のCO2削減コストが-13,700円/tCO2と推定されており、経済的効果も実証されています。
これらの技術動向は、JIS規格電気設備の分野が単なる安全基準の枠を超えて、環境性能や経済性も含めた総合的な技術体系として発展していることを示しています。建築従事者にとって、これらの最新動向を理解し適切に対応することが、今後ますます重要になってくるでしょう。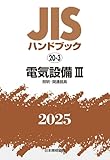
JISハンドブック 20-3 電気設備III[照明・関連器具] (2025)
