

働き方改革関連法2024による建設業の変更点
働き方改革関連法2024における時間外労働の上限規制
2024年4月から建設業に適用された働き方改革関連法により、時間外労働に罰則付きの上限規制が設けられました。これまで建設業では36協定を結ぶことで、時間の上限なく残業させることが可能でしたが、新たな規制により大きな転換を迎えています。
参考)建設業界の働き方改革・2024年問題を徹底解説!取り組み例も…
時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間となります。また、特別条項付き36協定を締結している場合でも、年720時間を超える時間外労働は認められません。さらに、特別条項の有無に関わらず、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2~6か月平均で80時間以内にする必要があります。
参考)2024年4月から始まる建設業の残業時間に対する罰則とは?概…
この規制の背景には、建設業で月100時間を超える長時間残業が横行していた実態があります。働き方改革関連法により、建設業の労働環境を他産業並みに改善し、労働者の健康と安全を守ることが目指されています。
参考)https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/001948230.pdf
働き方改革関連法2024の違反時の罰則内容
時間外労働の上限規制に違反した場合、厳しい罰則が科されます。具体的には、上限を超えて労働させた使用者に対し、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
参考)【2024年4月】建設業における時間外労働の上限規制とは?罰…
この罰則は企業にとって重大なリスクとなります。罰則を受けると労働基準法違反として記録が残り、企業の信頼性や入札参加資格にも影響を及ぼす可能性があるためです。また、違反が発覚した場合、労働基準監督署による是正勧告や指導が行われ、繰り返し違反する企業には厳しい処分が下されることもあります。
参考)2024年問題!建設業の時間外労働に対する罰則付き上限規制適…
建設業の経営者や現場責任者は、この罰則付き規制を十分に理解し、従業員に残業をさせずに事業を継続する方法を見出さなければなりません。法令遵守は企業存続の必須条件となっています。
働き方改革関連法2024における有給休暇取得義務の詳細
働き方改革関連法の施行により、2019年4月から年次有給休暇の取得義務化が適用されています。この制度では、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、企業は年5日以上の有給休暇を確実に取得させる義務があります。
参考)建設業界の有給休暇はどうなっている?経営者は正しい知識を持っ…
建設業における有給休暇の取得状況を見ると、令和5年度のデータでは労働者1人あたりの平均取得率は63.5%、平均取得日数は10.3日でした。これは全産業平均(取得率62.1%、取得日数10.9日)とほぼ同水準ですが、電気・ガス・熱供給・水道業の74.8%と比較すると、まだ改善の余地があります。
参考)建設業における有給休暇の取得状況と、取得率向上のための対策に…
建設業では人手不足や天候によって工程が左右されやすいという課題があり、有給休暇が取りづらい環境が続いていました。しかし、働き方改革により有給休暇の確実な取得と生産性の両立が求められるようになり、環境整備が進められています。
働き方改革関連法2024が建設業の労働環境に与える影響
働き方改革関連法の適用により、建設業の労働環境は大きく変化しています。これまでの取り組みによって、建設業の労働時間は他産業よりも大きく減少しましたが、なお高水準にあることが課題です。国土交通省の調査によると、建設業の年間労働時間は製造業と比べて約100時間、全産業と比べると約340時間も長い状況が続いています。
参考)建設業界における長時間労働の原因とは?対策方法やおすすめグッ…
2024年4月からの時間外労働の上限規制適用により、建設業では従来の働き方を抜本的に見直す必要が生じました。工期設定の適正化、週休2日制の導入、業務のDX化など、多面的な取り組みが求められています。また、若い世代が建設業界を敬遠する要因として「激務であるイメージ」が挙げられており、労働環境の改善は人材確保の観点からも重要です。
意外なことに、厚生労働省の試算では「もっと働きたい」と考えている就業者は全体の6.4%にとどまっており、長時間労働を望む労働者は少数派であることが明らかになっています。これは働き方改革の方向性が労働者のニーズと合致していることを示しています。
参考)「もっと働きたい」6%どまり 就業時間「変えたくない」7割超…
働き方改革関連法2024に対応する建設業の独自戦略
建設業が働き方改革関連法2024に対応するためには、業界特有の課題に応じた独自戦略が必要です。従来の人海戦術に頼る体質から脱却し、限られた労働時間で高い生産性を実現する体制づくりが求められます。
参考)建設業の生産性を向上させる3つの方法。成功事例・おすすめのツ…
まず注目すべきは、工程管理の最適化です。国土交通省の「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」では、発注者と受注者の両方に工期設定と施工時期を平準化するように示されています。工事の準備や片付けの時間、天候によって作業できない日のことも考え、余裕を持った工期設定を心がけることが重要です。
次に、組織体制の見直しも効果的な戦略です。ある中堅設備工事会社では「工務部」というミドルオフィスを新設し、現場との役割分担を明確化することで、業務負荷の低減と効率化を実現した事例があります。現場作業員が本来の施工業務に集中できる環境を整えることで、労働時間の削減と品質向上の両立が可能になります。
参考)建設業における働き方改革と業務効率化の実現:工務部の設立と現…
さらに、多能工の育成も建設業独自の有効な戦略です。一人の作業員が複数の職種の技能を持つことで、工程の柔軟性が高まり、効率的な人員配置が可能になります。これにより、特定の職種が不足する状況でも工事を進められるようになり、結果として残業時間の削減につながります。
参考)建設業の働き方改革を徹底解説!働き方改革事例も紹介 - Ci…
国土交通省や日本建設業連合会では、2025年度までに2020年度比で10%の生産性向上を目標として掲げており、建設業全体で働き方改革と生産性向上の取り組みが加速しています。
参考)生産性向上
国土交通省のICT活用推進ページでは、建設現場の情報をリアルタイムに見える化する取り組みを紹介しています
国土交通省「建設業における働き方改革推進のための事例集」では、実際の企業による具体的な取り組み事例が掲載されています
働き方改革関連法2024対応のICT活用事例
建設業における働き方改革の実現には、ICT(情報通信技術)の活用が不可欠です。国土交通省も「i-Construction」としてICTの全面的な活用を推進しており、調査・測量、設計、施工、検査等のあらゆる建設生産プロセスにおいてICTを導入する取り組みを進めています。
参考)「建設業2024年問題」の解決に向けたICT化の取り組み
具体的なICT活用事例として、以下のような取り組みが効果を上げています。
- ドローンによる測量作業の効率化:従来は人手で行っていた測量作業をドローンで実施することで、作業時間を大幅に短縮できます。3次元データを活用することで、設計段階から施工、検査まで一貫したデータ管理が可能になります。
- ICT建機の導入による省人化:3次元データと連動したICT建機を使用することで、少ない人員でも精度の高い施工が可能になり、工期短縮にもつながります。
- 遠隔臨場システムの活用:ウェアラブルカメラやタブレットを使った遠隔臨場により、現場に常駐する管理者を削減できます。これにより移動時間が減り、複数現場の効率的な管理が可能になります。
- 施工管理アプリの導入:現場でタブレットやスマートフォンを活用し、図面確認や進捗管理、報告書作成などをデジタル化することで、事務作業の時間を大幅に削減できます。
ICT化により作業効率が向上すれば、従業員の負担も軽減され、残業時間や休日出勤を低減できます。また、ICT技術によって危険が伴う作業を軽減させれば、従業員の安全性も高められます。建設業界の3Kイメージを払拭し、若者の就業意欲を向上させる効果も期待できます。
参考)建設業のICT化とは?ICTが必要な業務、実現化するためのツ…
国土交通省では、建設現場の情報をリアルタイムに見える化し、工程の見直しや作業の効率化を行うことで更なる省人化を目指す「ICT施工StageⅡ」の取り組みも開始しています。
参考)建設施工・建設機械:ICTの全面的な活用 - 国土交通省
トプコンの建設業ICT化解説記事では、具体的なICT導入のステップと効果が詳しく紹介されています
働き方改革関連法2024における週休2日制推進の現状
建設業における週休2日制の導入は、働き方改革の重要な施策の一つですが、現時点では義務化されておらず罰則もありません。国土交通省は「令和6年4月から、建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、直轄工事(公共工事)で計画的に週休2日を推進する」と発表しており、企業が自主的に取り入れることが目標とされています。
参考)建設業における週休2日制の義務化はいつから?導入のメリットと…
週休2日制を導入することで、労働者の長時間労働や時間外労働を防ぎ、休息時間を増やすことが可能です。リフレッシュすることで仕事へのモチベーション向上や業務効率の向上につながり、働きやすい職場が実現されます。また、他の業界と同じ週休2日制になれば企業としてもクリーンなイメージになり、若手の人材確保にもつながります。
建設業界の週休2日制推進には、適切な工期設定が不可欠です。国土交通省は「働き方改革・建設現場の週休2日応援サイト」を設置し、工期設定支援システムや工事着手準備期間・後片付け期間の見直しなど、週休2日実現のためのツールを提供しています。
参考)技術調査:働き方改革・建設現場の週休2日応援サイト - 国土…
実際に週休2日制を導入している企業では、計画的な工程管理と発注者の理解・協力を得ることで、工期内での完成と週休2日の両立を実現しています。しかし、天候によって工程が左右されやすい建設業の特性上、柔軟な工期設定と関係者の協力が重要となります。
参考)https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000717694.pdf
| 項目 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 週休2日制導入 | 計画的な休日取得の推進 | 労働時間削減、モチベーション向上 |
| 工期設定の適正化 | 準備・片付け期間を含めた余裕ある設定 | 無理のない工程管理の実現 |
| 発注者との連携 | 施工時期の平準化、工期の理解 | 安定した作業計画の実現 |
働き方改革関連法2024後の建設業における労働力確保策
働き方改革関連法2024の適用後、建設業界では労働力不足がさらに深刻化する懸念があります。建設業は高齢化が進んでおり、数年後には60歳以上の方が多く退職してしまい、今まで以上に人手不足が深刻になると言われています。
参考)建設業の2024年問題のその後とはーシリーズ:2024年の労…
この課題に対応するため、建設業では多角的な労働力確保策が求められています。
- 魅力的な労働環境の整備:労働時間の削減、週休2日制の導入、有給休暇の取得促進など、働きやすい環境を実現することで、若い世代の就業意欲を高めることができます。建設業界の3Kイメージを払拭し、「新3K(給料、休暇、希望)」を実現する取り組みが重要です。
- 賃金水準の向上:生産性向上による収益改善を労働者に還元し、賃金水準を向上させることで、建設業の魅力を高めることができます。
- 女性や高齢者の活躍推進:多様な人材が働きやすい環境を整備することで、労働力の裾野を広げることができます。ICT活用による負担軽減は、体力面でのハードルを下げる効果があります。
- 外国人材の受け入れ:適切な技能研修と労働環境の整備により、外国人材の活用も労働力確保の選択肢となります。
意外な事実として、建設業の2024年問題適用後、労働時間は大幅に減少したものの、年間収入は微減にとどまっており、時給換算では改善している企業も多く見られます。これは労働生産性の向上が一定程度実現していることを示しています。
採用市場では依然として人手不足感が強いものの、労働環境の改善により建設業への関心が徐々に高まっている傾向も見られます。働き方改革を契機として、建設業の魅力を再構築し、持続可能な人材確保の仕組みを作ることが、今後の業界発展の鍵となります。
参考)https://www.zenken.com/hinkaku/kousin/kousin_tekisuto/h28/02_sendai/konno.pdf
厚生労働省「働き方改革特設サイト」の建設業事例ページでは、時間外労働削減や幅広い人材活用に成功した企業の具体例が多数紹介されています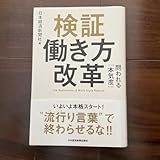
証 働き方改革

