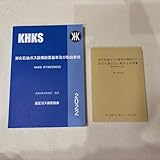液化石油ガス300kg消火器の設置基準
液化石油ガス300kg以上設置の届出要件
液化石油ガスを300kg以上貯蔵・使用する場合は、消防法に基づいて所轄の消防署への届出が必須となります。この300kgという基準は、ガスが気体化して膨張した際に広範囲へ拡散し、火元に接触すると爆発の危険性が高まるため、安全確保の観点から定められた重要な閾値です。届出手続きでは、設置場所、ガスの使用目的、配管やボンベの配置図などの詳細情報を記載した申請書を提出する必要があります。
参考)プロパンガス設置に関する消防法の基本と手続き【具体解説】 href="https://gastsubuyaki.com/2024/09/16/propangas-setting/" target="_blank">https://gastsubuyaki.com/2024/09/16/propangas-setting/amp;…
建築事業者は、設置工事を行う前に必ず最寄りの消防署へ申請を行い、消防署による安全性審査が完了してから初めて設置・使用が可能となります。500kg以上1000kg未満の貯蔵能力の場合は、消防法に加えて高圧ガス保安法にも該当し、消防署と都道府県知事の両方への届出が必要です。届出を怠ると法的な罰則が科される可能性があるため、事業者は確実に手続きを履行しなければなりません。
参考)電気と設備のノウハウ|なんとなく設備がわかる実践ガイド
液化石油ガス300kg未満と300kg以上の消火器能力単位の違い
液化石油ガスの貯蔵能力が300kg未満の場合は、消防法による届出義務はありません。しかし、300kg以上1t未満の貯蔵設備を設置する場合は、能力単位B-10の粉末消火器1個相当のものを設置することが液化石油ガス保安規則関係例示基準により定められています。一般的な事務所等に設置される10型消火器の消火能力はB-7であり、基準を満たしません。
参考)https://www2u.biglobe.ne.jp/~warriors/message/00292.html
高圧ガス関連施設で求められるB-10以上の消火能力を持つ消火器は、通常「20型」と呼ばれるタイプであり、消火能力はB-12となります。近年では、同じ消火薬剤量でも消火能力を著しく向上させた「高性能型消火器」が開発されており、10型サイズでB-10以上の能力を持つため、設置スペースの制約がある建築現場でも基準を満たすことが可能です。貯蔵量1t以上3t未満の場合は、設置容量に応じてABC粉末消火器(例:20型)を1本以上設置する必要があります。
参考)液化石油ガス・高圧ガス関係施設に高性能型消火器をおすすめする…
液化石油ガス300kg設置における火気との離隔距離基準
20L(約10kg)以上のガス容器を設置する際は、火気から2m以上の離隔距離を確保することが法律で義務付けられています。この「火気」には裸火だけでなく、スイッチ、コンセント、エアコンの室外機、自動販売機などの電気機器から発生するスパークも含まれます。液石法で規制される一般家庭や業務用のLPガス使用では、貯蔵量が1000kg未満の場合は火気から2m超、1000kg以上3000kg未満では5m以上の距離が必要です。
参考)LPガスと火気との距離、酸素と火気との距離について教えて下さ…
やむを得ず2m未満の距離しか確保できない場合は、供給管以上の高さの不燃材隔壁(コンクリートブロック、鉄板など)を設けることで対応可能です。高圧ガス保安法により規制される工業用LPガス使用や酸素の場合は、消費設備から5m超の離隔距離が求められます。建築事業者は、これらの離隔距離基準を正確に把握し、設計段階から適切な配置計画を立てる必要があります。
参考)https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/ekika_sekiyu/pdf/011_04_01.pdf
液化石油ガス300kg貯蔵設備の防消火設備設置義務
液化石油ガスの貯蔵能力が1t以上3t未満の貯蔵設備を設置する場合、貯蔵量に応じた消火器の設置が義務付けられています。貯槽以外の貯蔵設備(容器置場を含む)、処理設備、消費設備の中にある液化石油ガスの停滞量10tにつき、能力単位B-10の粉末消火器1個相当以上のものを設置する必要があり、最少設置数量は能力単位B-10消火器3個(容器置場にあっては2個)相当です。貯槽の場合は、防液堤を設置しているものは周囲に歩行距離75m以下ごとに、その他のものは貯槽の周囲の安全な場所に、能力単位B-10の消火器3個相当以上を設置することが求められます。
参考)http://kikenbutu.web.fc2.com/90_TUTATU/2018H30/H300330_2018323HO09/2018323HO09reiji2600.pdf
3t以上の貯蔵能力を持つ設備では、消火器に加えて屋外消火栓や防火水槽などの防消火設備の設置も必要となります。建屋内の高圧ガス設備については、不活性ガス等による拡散設備によって代替することも認められています。粉末消火器は、可搬性または動力車搭載のものであって、能力単位B-10以上のものでなければなりません。
参考)31. 防消火設備
液化石油ガス300kg設置における建築現場特有の安全管理体制
建築事業者が液化石油ガスを300kg以上設置・使用する場合、通常の工場や施設とは異なる特有の安全管理体制を構築する必要があります。建築現場では工事の進捗に伴い設備配置が変動するため、固定的な消火器設置計画だけでなく、現場の状況に応じた柔軟な配置変更と記録管理が求められます。LPガス設備の管理責任は、供給設備(容器からガスメーター出口まで)については販売店が、消費設備(ガスメーター出口からガス器具まで)については消費者(建築事業者)が負います。
参考)LPガス安全委員会:LPガスの正しい使い方 - 安全管理のポ…
建築現場では、定期供給設備点検(4年に1回以上)と定期消費設備調査(4年に1回以上)の保安業務を確実に実施することが法律で義務付けられています。現場責任者は、容器交換時等供給設備点検で容器の転倒防止状態を確認し、緊急時対応マニュアルを作業員全員に周知徹底することが重要です。また、建築現場特有のリスクとして、溶接火花や切断作業による火気が多いため、火気使用箇所からの離隔距離を常に確認し、不燃材隔壁の設置やガス検知器の配備など、多層的な安全対策を講じる必要があります。
参考)https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/anzen_torikumi/index.html
経済産業省の液化石油ガス保安規則関係例示基準では、消火設備の性能基準と設置基準の詳細が明記されています。
日本LPガス協会の安全管理ガイドでは、LPガスの正しい使用方法と安全管理のポイントが解説されています。
高圧ガス保安協会の行政手続きページでは、液化石油ガス設備工事の届出・変更届出の手続き方法が確認できます。
1210 液化石油ガス法