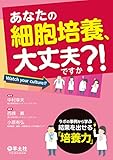細胞培養コンタミ見分け方
細胞培養における主要コンタミの視覚的特徴
細胞培養で最も頻繁に発生する細菌コンタミは、培養開始後数日以内に肉眼で確認できる典型的な症状を示します。培養液が濁って見えるようになり、液面に薄い膜状の構造物が観察されることがあります。フェノールレッド含有培地を使用している場合、細菌の代謝活動により培地のpHが急激に低下し、培地が黄色く変色する現象が特徴的です。
参考)https://www.thermofisher.com/blog/learning-at-the-bench/cell-culture-contamination/
低倍率の顕微鏡下では、細菌は細胞間を動き回る小さな顆粒状の構造物として観察され、高倍率では球形や桿状といった個々の細菌の形態を判別できます。一方で酵母汚染の場合、培地の濁りは発生しますが、重度に進行するまでpHはほとんど変化せず、進行後はpHが上昇する傾向があります。顕微鏡観察では卵形または球形の粒子として確認でき、出芽による分裂像が見られる点が細菌との重要な鑑別ポイントです。
参考)https://witc-rd.jp/column/researcher-38/
カビによる汚染も初期段階ではpHが安定していますが、汚染が進むと急激なpH上昇と培養液の濁りが生じます。顕微鏡下では薄く細いフィラメント状の菌糸体として観察されるか、密集した胞子の塊として現れることもあります。
Thermo Fisher Scientific「細胞培養でのコンタミの原因と対策」- 各種コンタミの詳細な視覚的特徴と顕微鏡画像
細胞培養マイコプラズマの特殊性と検出困難性
マイコプラズマは細胞壁を持たない特殊な細菌で、通常1μm未満という極めて小さいサイズのため、標準的な光学顕微鏡では検出が困難です。この微小さゆえに0.22μmの孔径を持つ標準的な滅菌フィルターでも通過してしまい、ろ過滅菌した培地でも汚染が発生する可能性があります。
参考)https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/cell-culture-troubleshooting-contamination
マイコプラズマ汚染の最も厄介な点は、培養液中で10⁸ organisms/mLという高密度にまで増殖しても培地に濁りを生じさせず、視覚的な検出が極めて難しいことです。また成長速度の遅いマイコプラズマ株は細胞を直接殺さずに長期間共存することがあり、この間も細胞の代謝や機能に深刻な影響を与え続けます。
参考)https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/cell-counting-and-health-analysis/mycoplasma-detection-and-elimination
感染した細胞培養では、細胞増殖速度の低下、飽和密度の減少、浮遊培養における細胞凝集などの間接的な兆候が現れることがありますが、これらは他の培養条件の問題とも区別が困難です。マイコプラズマは細胞に染色体異常を誘発し、代謝経路を変化させるため、汚染された細胞株を用いた実験結果の信頼性は著しく損なわれます。
💡 意外な事実:マイコプラズマの一部の種はヒトの皮膚にも常在しているため、不適切な無菌操作により作業者自身がマイコプラズマの感染源となるケースが報告されています。
細胞培養コンタミ検出における三大手法の比較
細胞培養におけるコンタミ検出法は、培養法・DNA染色法・PCR法の3つが主流となっており、それぞれ異なる特徴を持ちます。
参考)https://iptec.sanplatec.co.jp/news/cell-culture-mycoplasma/
培養法は、マイコプラズマ専用培地に検体を接種し寒天平板上でコロニー形成を確認する直接検出法です。この方法は約4週間という長い検査期間を要しますが、確実な検出が可能で、培養細胞だけでなく試薬の汚染検査にも利用できる点が利点です。マイコプラズマ感染がある場合、培地プレート上に特徴的な目玉焼き状のコロニーが観察されます。
DNA染色法は、Hoechst 33258やDAPIなどの蛍光色素を用いてマイコプラズマの核DNAを染色し、蛍光顕微鏡で観察する方法です。この方法は72時間以内に結果が得られる迅速性が最大の利点ですが、マイコプラズマの確定診断には至らず、他のDNA含有物質との鑑別が必要という制約があります。
参考)https://m-hub.jp/biology/2138/133
PCR法は培養細胞から採取したDNAを増幅させ、マイコプラズマの遺伝子を特異的に検出する方法です。極めて高い感度と迅速性を兼ね備え、リアルタイムPCRを用いることで定量的な測定も可能になります。培養細胞に混入するほとんどのマイコプラズマ種を検出でき、現在最も信頼性の高い検出法として広く採用されています。
参考)https://www.funakoshi.co.jp/contents/8195
| 検出方法 | 所要時間 | 感度 | 確実性 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 培養法 | 約4週間 | 中 | 高 | 試薬検査・最終確認 |
| DNA染色法 | 72時間以内 | 中 | スクリーニング | |
| PCR法 | 数時間~1日 | 極めて高 | 定期検査・確定診断 |
Sigma-Aldrich「細胞培養のコンタミネーションに関するトラブルシューティング」- 各検出法の詳細なプロトコルと比較
細胞培養における無菌操作の実践的ポイント
細胞培養におけるコンタミ予防の基本は、徹底した無菌操作の実践です。作業開始前には必ずバイオセーフティキャビネットの作業台を70%アルコールで消毒し、手袋にもアルコールを噴霧して30秒間乾燥させます。キャビネット内に持ち込むすべての器具や試薬ボトルは、事前に70%アルコールを噴霧したワイプで拭いて汚染物質を除去する必要があります。
参考)https://www.sigmaaldrich.com/JP/ja/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/aseptic-technique
ピペット操作では、自動ピペットエイドを使用し、各エイドは1つのキャビネット専用として管理することが重要です。特に培地移送時にはプラグ付きピペットを使用し、プラグ内まで液体を吸引しないよう注意が必要です。万が一プラグを濡らした場合は、速やかにピペットエイドフィルターを交換しなければなりません。
作業中はキャビネット内の空気の流れを乱さないよう、ゆっくりとした動作を心がけ、キャビネット外のもの(特に顔や髪)に触れて手袋を汚染しないよう細心の注意を払います。会話や咳、くしゃみはキャビネットから離れた場所で行い、やむを得ず会話が必要な場合は作業場所から顔を背けるようにします。
培養室専用の白衣や履物を使用し、長い髪は後ろで縛るかキャップを着用することで、皮膚や毛髪からのほこりが培養液に落下するリスクを軽減できます。培養フラスコや培地ボトルはスクリューキャップで密閉し、インキュベーターや冷蔵庫から取り出す際は必ず70%アルコールで拭いてからキャビネット内に持ち込みます。
⚠️ 重要な注意点:液体の注ぎ移しは極力避け、必ずピペットやオートディスペンサーを使用してください。注ぐ動作はボトルのネックや外側への培地の付着を引き起こし、深刻なコンタミ源となります。
細胞培養施設における環境管理と設備保守
細胞培養におけるコンタミ予防では、作業者の無菌操作技術だけでなく、施設環境と設備の適切な管理が不可欠です。実験室の設計、換気システム、気流パターンはエアロゾルや浮遊粒子の分散に直接影響するため、細胞培養専用の区画を確保し、人の通行を最小限に抑える必要があります。
参考)https://www.funakoshi.co.jp/contents/72263
ラミナーフローのバイオセーフティキャビネットは、その機能について定期的な認証と点検が必須です。作業の前後に最低15分間はラミナーフローを稼働させ、キャビネット内の空気を浄化することが汚染リスク低減に役立ちます。HEPAフィルターは定期的に穴や漏れがないか点検し、吸引圧力の低下が見られた場合は速やかに交換が必要です。
CO₂インキュベーターとウォーターバスは微生物増殖に理想的な環境条件を提供するため、特に注意深い管理が求められます。インキュベーター内は定期的に清掃し、メーカーの仕様に従って適切に消毒する必要があります。強制空気循環により運ばれる胞子などから培養物を保護するため、蓋のないディッシュは密閉しないプラスチック製ボックスに入れて保管します。
ウォーターバスは特にカビや細菌の温床となりやすいため、定期的な清掃と消毒が不可欠です。可能であれば、水を使用しないビーズ式加温槽の導入を検討することで、このリスクを大幅に低減できます。床や実験台、流し台、試薬棚など施設全体の環境を清潔に保つための定期的な清掃作業も、環境汚染を最小限に抑えるために有用です。
細胞培養施設への入室は制限し、空気中の汚染物質濃度が高まらないよう、施設内の人数が過密にならないよう管理することがマイコプラズマ汚染リスクの低減につながります。
細胞培養コンタミ発生時の廃棄と消毒プロトコル
コンタミが発見された培養物は、周辺の培養系への伝播を防ぐため直ちに隔離し、適切に廃棄する必要があります。液状の細胞培養廃棄物は、次亜塩素酸ナトリウム溶液(10,000 ppm)で処理し、キャビネット内に最低2時間、できれば一晩放置してから多量の水とともに廃棄します。
消毒剤の選択は汚染物質と処理対象によって使い分けが重要です。次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤)は一般用途に優れた消毒剤で、ウイルスに対しても有効ですが、金属面への腐食性があるため遠心分離機などの金属設備には使用できません。市販の漂白剤を10%(v/v)に希釈した溶液が廃液処理と表面消毒に適していますが、有機物により速やかに不活化されるため頻繁に新しく調製する必要があります。
アルコール系消毒剤は、エタノール70%またはイソプロパノール60~70%の濃度が有効です。エタノールは大半のウイルスと細菌に有効ですが、ノンエンベロープウイルスには無効で、イソプロパノールはウイルス全般に対して効果が限定的です。作業台の表面消毒には70%エタノールが広く使用されていますが、用途に応じて適切な消毒剤を選択することが重要です。
コンタミが疑われる細胞株を新たに入手した場合は、単独で取り扱い可能な限り隔離します。抗生物質を使用せずに2週間培養して汚染をチェックし、位相差顕微鏡観察やマイコプラズマ用のHoechst/DAPI染色により視覚的確認を行います。キャビネットの表面は定期的に消毒液で洗浄するか、メーカーの指示に従って燻蒸消毒を実施しますが、ホルムアルデヒドガスを使用する燻蒸では安全性の確認が必須です。
Corning「細胞培養コンタミネーションの原因を取り除くには」- 化学的汚染物質を含む包括的な汚染源と対策