

用途地域一覧
用途地域とは、都市計画法に基づいて市街化区域を13種類に区分し、それぞれの地域で建築可能な建物の種類や規模を制限する制度です。この制度により、計画的な市街地の形成と良好な居住環境の保護が実現されています。建築業従事者にとって、用途地域の理解は建築計画の初期段階で極めて重要な要素となります。
参考)https://house.home4u.jp/contents/land-11-7324
用途地域は大きく「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分類され、全国で最も多く指定されているのは第一種住居地域で全体の23%を占めます。次いで第一種低層住居専用地域が18%、第一種中高層住居専用地域が14%となっており、住居系用途地域が全体の67%を占めています。
参考)https://www.token.co.jp/estate/column/estate-library/131/
建築基準法では、各用途地域に対して建ぺい率や容積率、高さ制限などの詳細な規制を設けており、これらの制限を正確に把握することが建築計画の成否を左右します。用途地域による制限は、建物の種類だけでなく、敷地面積に対する建築面積や延床面積の比率にも及びます。
参考)https://iezukuri-business.homes.jp/column/construction-00031
用途地域13種類の特徴と建築制限
各用途地域には明確な目的と建築制限が設定されています。住居系地域では、第一種低層住居専用地域が最も厳しい制限を持ち、建ぺい率は30~60%、容積率は50~200%の範囲で定められます。この地域では、建物の高さが10mまたは12m以下に制限される絶対高さ制限が適用され、閑静な住宅環境が保護されています。
参考)https://www.e-a-site.com/knowledge/rules/capacity/
第一種中高層住居専用地域では、中高層住宅の建築が可能となり、病院や大学、500㎡までの一定の店舗が建てられます。建ぺい率は50~80%、容積率は100~500%と、低層住居専用地域よりも高い数値が設定されています。
参考)https://www.polus.jp/column/article/?n=100
商業系地域では、近隣商業地域の建ぺい率が60~80%、商業地域が80%となり、容積率は商業地域で最大1300%まで認められます。商業地域は銀行や映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域として定められ、利便性の高い都市機能の集積が図られています。
参考)https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/other/youtochiiki/
国土交通省「用途地域の種類」では各用途地域の法的根拠と詳細な建築制限が確認できます
用途地域の建ぺい率と容積率の関係
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の上限を定めた数値で、容積率は敷地面積に対する延床面積の上限を定めた数値です。建ぺい率が敷地に対する平面の割合を制限しているのに対し、容積率は立体の大きさを制限しています。
参考)https://sfc.jp/ie/myhome/articles/kenpei-youseki20250725/
用途地域別の建ぺい率と容積率は以下のように定められています:
| 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 30、40、50、60 | 50、60、80、100、150、200 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 30、40、50、60 | 100、150、200、300、400、500 |
| 第一種住居地域 | 50、60、80 | 100、150、200、300、400、500 |
| 近隣商業地域 | 60、80 | 100~500 |
| 商業地域 | 80 | 200~1300 |
| 準工業地域 | 50、60、80 | 100~500 |
| 工業地域 | 50、60 | 100、150、200、300、400 |
| 工業専用地域 | 30、40、50、60 | 100、150、200、300、400 |
住居系地域では建ぺい率と容積率が低めに設定されており、建ぺい率は30~80%、容積率は50~500%の中から定められます。これにより、居住環境を優先した適切な空間確保が実現されています。
参考)https://t816.jp/column/building-standard/
商業地域では利便性が高いため地価も高く、それに応じて高い容積率が認められています。一方、工業専用地域は利用目的が限定されるため相対的に地価が低く、用途地域による評価額の差は固定資産税や都市計画税にも影響を与えます。
参考)https://jutaku-ichiba.com/column/%E7%94%A8%E9%80%94%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F-%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%AB%E8%BA%AB%E8%BF%91%E3%81%AA%E3%80%8C%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%B3%95%E3%80%8D/
用途地域の高さ制限と斜線制限
用途地域には建ぺい率・容積率以外に、建物の高さに関する制限が設けられています。高さ制限は大きく分けて「絶対高さ制限」「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」の4種類があります。
参考)https://sell.yeay.jp/reading/knowledge/10103/
絶対高さ制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域にのみ適用される制限で、建物の高さが10mまたは12m以下に制限されます。これらの用途地域では原則として10mまたは12m以上の建築物は建てられないため、隣地斜線制限は適用されません。
参考)https://www.e-a-site.com/knowledge/rules/height/
道路斜線制限は、道路の日照や通風を確保するための制限で、用途地域によって適用距離や勾配が異なります。北側斜線制限は、北側隣地の日照を確保するために、第一種・第二種低層住居専用地域と第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されます。
参考)https://www.megasoft.co.jp/3d/setback_regulation/height_basic.php
高度地区が指定されている地域では、さらに詳細な高さ制限が設けられる場合があります。名古屋市などの自治体では、用途地域・指定容積率や市街地の現況等をふまえ、段階的に建物の高さの設定を行う高度地区制度を運用しています。
参考)https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000002/2287/ayemxwt6wrwzwv_isgsy1_j.pdf
国土交通省「建築物の高さ制限について」では斜線制限の詳細な計算方法が確認できます
用途地域における工業系地域の建築制限
工業系の用途地域は「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」の3つに分類され、地域ごとに規制が大きく異なります。建築業従事者にとって、これらの地域における建築制限の理解は工場や倉庫の建設計画において不可欠です。
参考)https://kensetsu-hyogo.com/article/qa/eigyosyo/2117/
準工業地域は、危険性や環境悪化が大きい工場を除いて、軽工業をはじめとするさまざまな施設を建築できる地域です。この地域では学校や病院、商業施設、ホテル、住宅などの建物も建てられ、さまざまな施設が混在する街並みとなります。建ぺい率は50・60・80%、容積率は100・150・200・300・400・500%のいずれかが指定されます。
参考)https://sanyoukensetsu.co.jp/column/894/
工業地域では、どんな工場でも建てられますが、住宅やお店は建てられるものの、学校・病院・ホテルなどは建てられません。工業専用地域は、その名の通り工業専用となるため住宅は建てられず、工場のための地域として位置づけられています。
参考)https://marumine.net/blog/landselection/27655.html
用途地域に指定されていない土地に工場を建てることも可能ですが、インフラ未整備の可能性があり、建設コストが大幅に増えるリスクがあります。水道、ガスなどのインフラ引き込みなど、通常の工業団地にはない追加投資が必要となる場合があります。
参考)https://yamaura.co.jp/column/land-requirements-and-regulations-for-factory-construction/
e-Gov「都市計画法」では用途地域の法的根拠と詳細が確認できます
用途地域の調べ方と確認方法
用途地域を調べる方法は、オンラインと対面での確認方法に大きく分かれます。建築確認申請などで正確な情報が必要な場合は、複数の方法を組み合わせることが推奨されます。
参考)https://housemarriage.net/column/basic/column-2808/
オンラインでの確認方法として、多くの自治体が独自の地理情報システム(GIS)を提供しており、ウェブブラウザ上で地図を操作しながら該当地域の用途地域を確認できます。用途地域マップでは、国土交通省国土政策局の国土数値情報を基に作成された地図データが公開されており、全国の用途地域を調べることが可能です。
参考)https://www.zenrin-datacom.net/solution/blog/use-districts
国土交通省が運営する「国土数値情報ダウンロードサービス」では、全国の用途地域について行政区域コード、都道府県名、市区町村名、用途地域分類コード、用途地域名、建ぺい率、容積率等のデータを入手できます。このデータは定期的に更新され、信頼性の高い情報源として知られています。
参考)https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A29.html
対面での確認方法として、市区町村の都市計画課での確認が最も確実な方法の一つです。都市計画図の閲覧が可能で、専門の職員に直接相談することもでき、特に建築確認申請などで必要となる証明書の発行もここで行うことができます。物件の住所や地番がわかれば、正確な用途地域を確認することが可能です。
参考)https://www.homes.co.jp/cont/buy_kodate/buy_kodate_00615/
一宮市では「138マップ」という地図情報サイトを提供しており、区域区分や用途地域、都市計画道路などの都市計画情報をウェブサイト上で確認できます。ただし、都市計画情報は地図作成上の誤差を含んでいるため、都市計画の境域と地形地物に対する詳細な位置関係を知りたい場合は、担当課の窓口で確認する必要があります。
参考)https://www.sonicweb-asp.jp/ichinomiya/agreement?theme=th_90amp;layers=th_86%2Cdm
国土交通省「国土数値情報ダウンロードサービス」では全国の用途地域データが無料でダウンロードできます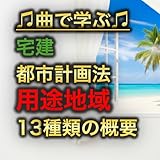
宅建 都市計画法_用途地域13種類の概要

