

電子情報技術産業協会の標準化活動
電子情報技術産業協会(JEITA)の概要と組織体制
一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)は、2000年11月に日本電子工業振興協会(JEIDA)と日本電子機械工業会(EIAJ)が統合して誕生した、エレクトロニクスや電子機器、情報技術(IT)に関する日本最大級の業界団体です。2005年には日本電子材料工業会(EMAJ)を統合・吸収し、さらに組織を拡大しました。現在は一般社団法人として、日本の電子情報産業の発展と振興を目的に幅広い活動を展開しています。
参考)電子情報技術産業協会 - Wikipedia
JEITAには、日本を代表する大手電機メーカーや電子部品メーカーなど約250社が会員として参加しており、総会や理事会、各種委員会を通じて活発な意見交換と情報共有が行われています。2025年からは漆間啓三菱電機代表執行役執行役社長CEOが会長に就任し、新たな体制のもとで業界をリードしています。組織は情報・産業システム部会、AVC部会、半導体部会、電子部品部会など複数の部会で構成され、各分野の専門性を活かした事業活動を推進しています。
参考)部会概要
JEITAの主な事業内容は、標準規格の策定、市場調査および統計の発表、展示会の開催、業界の利益代表として各界への政策提言などです。特にエレクトロニクス分野で国内最大級の国際展示会「CEATEC」や、放送機器の国際展示会「Inter BEE」の主催団体として知られており、最新技術やイノベーションの発信拠点となっています。
参考)JEITA(電子情報技術産業協会)とは?意味を分かりやすく解…
電子情報技術産業協会のJEITA規格制定と国際標準化対応
JEITAの標準化活動は、国際規格(IEC、ISO、JTC1等)および国内規格(JIS)を基本としながら、これらを補完する業界団体規格としてJEITA規格の制定・発行を行っています。JEITA規格は、現行国際規格体系に則り、必要とする標準化体系を作成するとともに、対応国際規格のない新規制定JISについては国際規格提案を前提に作成され、積極的に国際標準化を推進しています。
参考)https://www.jeita.or.jp/japanese/public/pdf/hyoujunkaGB_2022.pdf
JEITA規格のカテゴリー構成は体系的に整理されており、ET(電子工業一般)、TT(情報通信機器)、AE(電子応用機器)、CP(民生用電子機器)、RC(一般電子部品)、ED(電子デバイス)、EM(電子材料)、IT(情報処理関連)の8つの分野に分類されています。各分野において、部品一般から電子デバイス、情報処理まで、0000~1999の番号体系で規格が管理されており、産業界のニーズに応じた規格整備が進められています。
国際標準化活動においては、JEITAは日本産業標準調査会(JISC)から多くのTC/SC/TA等の国内審議団体を受託し、各々の国内委員会を運営しています。IEC(国際電気標準会議)のTC47(半導体デバイス)をはじめとする複数の技術委員会において、IECの国内委員会と連携しながら国際標準規格の日本提案と各国提案内容の審議を実施しています。また、開発した国際規格やJEITA規格の普及促進を図るため、セミナーやワークショップの開催、自動車などの関連業界活動との連携など、積極的な普及活動を展開しています。
参考)JEITAで対応する国際標準化活動|JEITA
JEITA規格の詳細情報と最新の標準化活動状況
標準化委員会では、規格(IEC規格、JIS)に関する基本的な作成方法を実践を交えながら学ぶ機会を年2回開催しており、国際会議での交渉術についても講師の経験談を交えた実用的な講義を提供しています。こうした人材育成の取り組みにより、日本の国際標準化活動における競争力強化に貢献しています。
参考)https://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=1292
電子情報技術産業協会と建設業界の接点と水中インフラ点検技術
建設業界とJEITAの接点として注目されるのが、水中インフラ点検技術の開発です。JEITAの「共創プログラム」として設立されたALAN(Aqua LAN)コンソーシアムでは、水中ライダ(LiDAR)、水中光無線給電、水中光無線通信など水中光無線技術の検討が行われています。特に建築年度が判明している橋りょう、港湾岸壁、及び河川管理施設の大半が2033年までに建築後50年を突破すると試算されており、水中構造物の点検など日本のインフラ維持への適用が期待されています。
参考)水中ライダ──水中における可視光3Dスキャンライダの開発──
水中環境は音波等限られた手段しか使えない「最後のディジタルデバイド領域」とされていましたが、JEITAの取り組みにより、水中を一つの生活圏と捉え、水中にLocal Area Network(LAN)を構築する技術開発が進められています。従来の電磁波による給電、電磁波や音波による距離測定や通信に加え、可視光を使った水中ライダなどの革新的技術により、水中環境の詳細データをリアルタイムに地上に転送する通信ネットワークの構築が可能になりつつあります。
建設事業者にとって、こうした水中モニタリング技術は、老朽化が進むインフラの維持管理において重要なツールとなります。水中ライダを使った水中構造物の点検は、従来の潜水士による目視点検と比較して、安全性の向上、作業効率の改善、データの定量化・記録化などのメリットがあり、今後の建設業界における新たな技術標準として普及が見込まれています。水中ロボティクスと組み合わせることで、遠隔からの水中作業も可能になり、建設業界のDX推進にも貢献する技術です。
電子情報技術産業協会の環境・サーキュラーエコノミー推進活動
JEITAは、持続可能な社会の実現に向けた環境活動にも積極的に取り組んでいます。2025年4月には、電機・電子4団体(JEITA、JEMA、CIAJ、JBMIA)共同で「電機・電子業界サーキュラーエコノミービジョン」を策定しました。このビジョンでは、サーキュラーエコノミーのグローバル原則や各国・地域の新たな政策等を踏まえ、電機・電子業界としての姿勢を明確に表明しています。
参考)「電機・電子業界サーキュラーエコノミービジョン」を策定
サーキュラーエコノミー実現の道筋として、企業自らが循環型経済への取り組みを進める「Adopters」としての役割と、技術やソリューションの提供を通じて社会全体の循環性向上に貢献する「Enablers」としての役割を両輪で推進していく方針が示されています。建設業界においても、建設廃棄物のリサイクルや資源循環が重要課題となっており、電機・電子業界との連携により、より効率的な循環型社会の構築が期待されています。
参考)電機・電子業界サーキュラーエコノミー(CE)ビジョン
またJEITAは、2050年カーボンニュートラルに向けた産業横断の取り組みも推進しており、ヒートポンプ等を活用したCO2削減への取り組みなど、地球温暖化対策にも注力しています。建設業界における省エネルギー技術の導入や、環境配慮型建築の推進において、JEITAが策定する環境関連規格や技術基準が参考になる場面も増えています。
参考)https://www.semanticscholar.org/paper/c1f47d7fa944516d35bc1edb01d25ce0db1ed698
欧州サーキュラーエコノミーの動向視察なども行っており、グローバルな視点から日本の産業界に最新情報を提供することで、建設業界を含む各産業のサステナビリティ向上に貢献しています。政府、投資家、関連業界等のステークホルダーに対して電機・電子業界の立場を明示しつつ、各社における取組の方向性を示すことで、業界全体の底上げを図っています。
電子情報技術産業協会の調査統計事業と建設業界への応用可能性
JEITAでは、電子情報産業の幅広い製品分野の市場動向をタイムリーに把握するため、さまざまな調査統計事業を実施しています。「JEITA調査統計ガイドブック」では、業界統計、自主統計、分野別市場動向、統計分類、市場規模、調査統計イベントスケジュールなどを分かりやすくまとめており、会員各社をはじめとする内外企業の事業計画立案や市場分析に活用されています。
参考)https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/public/detail.cgi?id=937amp;cateid=1
2023年の電子情報産業の世界生産額は対前年3%増の3兆5,266億ドルと過去最高を更新しており、デジタル化の進展やデータ活用の高度化・自動化によるソリューションサービスの増加により成長を続けています。今後は、各国でデジタルイノベーションにより社会や企業・産業を変革する動きが進むことから、ソリューションサービスの伸長が期待されています。
参考)https://www.jeita.or.jp/japanese/stat/pdf/executive_summary_2023_2024.pdf
建設業界においても、BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)の導入が進み、デジタルトランスフォーメーション(DX)が加速しています。JEITAの統計データや市場分析手法は、建設事業者が新店舗の出店計画や新商品の開発といった重要な経営判断を行う際に、客観的な根拠を提供します。統計データの活用により、主観や思い込みによる失敗のリスクを最小限に抑え、成功の確度を高めることができます。
電子部品部会の調査統計委員会では、「電子部品企業のグローバル動向調査」、「電子部品の世界需要額推計」、「主要電子機器の世界生産状況調査」の3つの調査を実施しており、JEITA関連委員会をはじめとする国内外関係先との交流を積極的に進め、多面的な情報収集と分析を行っています。こうしたグローバルな視点からの市場分析は、建設業界が海外展開を検討する際の重要な参考情報となります。
参考)傘下委員会
電子情報技術産業協会が主催する展示会とビジネスマッチング機会
JEITAが主催する主な展示会として、「CEATEC」と「Inter BEE」があります。CEATECは毎年開催される国内最大規模のデジタルイノベーションの総合展示会で、2025年は10月14日~17日に幕張メッセで開催されました。ホール1~ホール6までを使用し、過去3年を超える規模での開催となり、Society 5.0が実現する未来を解説する場として、最先端技術やイノベーションが一堂に会します。
参考)「CEATEC 2025」14日から開催! 注目のコンファレ…
Inter BEE(国際放送機器展)は、2025年11月19日~21日に幕張メッセで開催される、国内最大規模の放送関連機器の展示会です。メディア&エンターテインメント産業における技術の進展を背景に、特にAIを活用した新たな技術・製品の展示が充実しており、61回目となる2025年は新たな進化のスタート年として位置付けられています。展示規模は昨年以上に拡大し、幕張メッセの展示ホール2~8ホール、国際会議場、イベントホールを使用して開催されます。
参考)Inter BEE、来場事前登録を公式サイトで開始
これらの展示会は、日本エレクトロニクスショー協会(JESA)が準備し出展を募っており、建設業界の事業者にとっても、最新の電子技術やデジタルソリューションに触れる貴重な機会となります。特にスマートビルディングやIoT技術、AI活用など、建設業界のDX推進に関連する技術が多数展示されており、新たなビジネスパートナーとの出会いや技術導入の検討に活用できます。
JEITAからのお知らせと最新イベント情報
CEATECのテーマは「Smart Innovation――未来をつくる最先端技術」であり、暮らしや社会、ビジネスのためのスマート・イノベーションを提案し世界へ発信する場となっています。建設業界においても、スマートシティ構想やエネルギーマネジメントシステムの導入など、こうした最先端技術との連携が求められており、展示会への参加を通じて業界を超えた共創の機会を得ることができます。
参考)【ニュース】CEATEC 出展募集を開始 開催テーマは「S…
建設事業者がこれらの展示会に参加することで、電子情報技術の最新動向を把握し、自社の業務効率化や新たなサービス開発のヒントを得ることができます。また、JEITAが推進する「JEITA共創プログラム」では、業種・業界を超えた共創によるイノベーションを促し、新たな市場の創出を目指しており、建設業界との協業の可能性も広がっています。
参考)事業内容
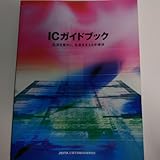
ICガイドブック JEITA 社団法人 電子情報技術産業協会
