

地盤調査と建築
地盤調査の目的と建築物の安全性
地盤調査は、建築物を設計・施工する際に欠かせない重要なプロセスです。その主な目的は、建物の安全性と経済性を確保することにあります。
地盤調査を行わずに軟弱な地盤上に建物を建てると、以下のようなリスクが生じます。
阪神淡路大震災の教訓から、2000年に建築基準法が改正され、地盤調査が法的に義務付けられました。これにより、建物の構造計算に必要な地盤の許容応力度を適切に算出するための調査が必須となっています。
地盤調査の結果は、建物の基礎設計に直接反映され、適切な基礎工法の選定や地盤改良の必要性判断に活用されます。つまり、地盤調査は建物の「土台」となる部分の品質を確保するための重要なステップなのです。
地盤調査の種類と代表的な手法
建築物の地盤調査には、規模や目的に応じていくつかの手法があります。それぞれの特徴を理解し、適切な調査方法を選択することが重要です。
1. SWS試験(スクリューウエイト貫入試験)
戸建住宅の地盤調査として最も普及している方法です。2020年10月にJIS規格が改正され、旧「スウェーデン式サウンディング試験」から名称が変更されました。
- 調査方法: 地盤にロッド(鉄の棒)を垂直に突き刺し、その沈み方から地盤の硬軟や締まり具合を調査
- 調査期間: 半日程度
- 調査ポイント: 一般的に敷地の4隅と中央の5ポイント
- 特徴: コストが比較的安く、短時間で結果が得られる
2. ボーリング調査
より詳細な地盤情報を得るための調査方法です。大規模な建築物や特殊な地盤条件の場合に採用されます。
- 調査方法: 専用の機械で地中に穴を掘り、地層の構成や地下水位を確認
- 調査期間: 数日かかる場合もある
- 特徴: 地中深くまで調査可能で、精度の高いデータが得られる
3. 平板載荷試験
実際に建物の重量に相当する負荷をかけて沈下の度合いを測定する試験です。
- 調査方法: 地盤に対して実際の荷重をかけ、沈下量を測定
- 特徴: プレハブなどの簡易な建物の建設に適している
これらの調査方法は、建築物の規模や地域の地盤特性に応じて選択されます。複数の調査方法を組み合わせることで、より正確な地盤評価が可能になります。
地盤調査と建築基準法の関係性
地盤調査は単なる任意の調査ではなく、建築基準法によって明確に義務付けられています。この法的根拠を理解することは、建築に携わる専門家にとって不可欠です。
建築基準法における地盤調査の位置づけ
建築基準法施行令第38条と第93条には、地盤の許容応力度と基礎杭の許容支持力について、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならないと規定されています。具体的な調査方法は国土交通省告示1113号に定められています。
2000年の法改正の意義
阪神淡路大震災の教訓を踏まえ、2000年に建築基準法が改正され、地盤調査が明確に義務付けられました。それ以前は明確な義務付けがなかったため、2000年以前に建てられた建物では適切な地盤調査が行われていない可能性があります。
建て替え時の地盤調査の必要性
既存建物の建て替えの場合でも、新たに地盤調査を実施する必要があります。これは以下の理由によります。
- 建築当時と現在では地盤状況が変化している可能性がある
- 2000年以前の建物では適切な地盤調査が行われていない可能性がある
- 新しい建物の荷重条件が異なる場合がある
地盤調査を怠ると、建築確認申請が受理されないだけでなく、将来的な建物の安全性にも関わる重大な問題となります。法令遵守の観点からも、適切な地盤調査の実施は不可欠です。
地盤調査結果の見方と活用方法
地盤調査を実施した後、その結果をどのように解釈し、建築計画に活かすかが重要です。ここでは、調査結果の基本的な見方と活用方法について解説します。
N値の理解
地盤調査の結果で最も重要な指標の一つが「N値」です。これは地盤の固さを示す数値で、値が大きいほど地盤が固いことを意味します。
- N値 < 2:非常に軟弱な地盤
- N値 2〜4:軟弱な地盤
- N値 4〜8:やや軟弱な地盤
- N値 8〜15:中程度の地盤
- N値 15〜30:やや固い地盤
- N値 > 30:固い地盤(良好な支持層)
地層構成の分析
調査結果には地層の構成も示されます。一般的な地層には以下のようなものがあります。
- 表土・盛土:人工的に造成された層で、一般に支持力は期待できない
- 粘性土層:粘土やシルトからなる層で、水を含むと軟弱になりやすい
- 砂礫層:砂や小石からなる層で、比較的支持力がある
- ローム層:火山灰からなる層で、関東地方に多く見られる
- 岩盤:最も支持力のある層
調査結果の活用方法
地盤調査の結果は、以下のような建築計画の重要な判断材料となります。
- 基礎形式の選定:直接基礎(ベタ基礎、布基礎など)か杭基礎かの判断
- 地盤改良の必要性判断:表層改良、柱状改良、小口径鋼管杭などの選択
- 構造計算への反映:建物の構造設計における地盤の許容応力度の設定
- コスト計画への反映:地盤改良費用の予算化
適切な地盤調査結果の解釈により、過剰な地盤改良を避けつつ、安全性を確保した経済的な建築計画が可能になります。
地盤調査から見る災害リスクと対策
地盤調査は建物の安全性確保だけでなく、自然災害に対するリスク評価と対策立案にも重要な役割を果たします。特に日本のような地震大国では、地盤特性と災害リスクの関連性を理解することが不可欠です。
液状化現象のリスク評価
地盤調査では、液状化の可能性がある砂質地盤の特定が可能です。液状化とは、地下水位が高く砂の地層が地震の揺れによって液体のようになり、建物が沈下する現象です。
液状化リスクの高い地盤の特徴。
- 地下水位が高い(地表から3m以内)
- 緩い砂質土で構成されている
- N値が10以下の砂層がある
地すべり・崖崩れのリスク評価
傾斜地や丘陵地の地盤調査では、地すべりや崖崩れのリスク評価も重要です。地層の傾斜角度や地下水の状況、風化度合いなどから、将来的な地盤変動のリスクを予測できます。
災害リスクへの対策
地盤調査で特定されたリスクに対しては、以下のような対策が考えられます。
- 液状化対策。
- 地盤改良(深層混合処理工法など)
- 杭基礎の採用
- ドレーン工法による地下水位の低下
- 地すべり対策。
- 抑止杭の設置
- 地下水排除工
- 法面保護工
- 軟弱地盤対策。
- 表層改良
- 柱状改良
- プレロード工法(事前荷重工法)
地盤調査で得られた情報を基に、建築計画段階から災害リスクを考慮した設計・施工を行うことで、将来的な被害を最小限に抑えることができます。特に近年の気候変動に伴う豪雨の増加により、これまで安全とされてきた地域でも地盤災害のリスクが高まっていることに注意が必要です。
地盤調査会社の選び方と信頼性確保
地盤調査の結果は建物の安全性に直結するため、信頼できる調査会社の選定が極めて重要です。2021年には四国の地盤調査会社で不正が発覚するなど、調査結果の信頼性に関わる問題も発生しています。
信頼できる地盤調査会社の選定基準
- 資格保有者の在籍
- 地質調査技士
- 土木施工管理技士
- 地盤品質判定士などの専門資格者が在籍している
- 実績と経験
- 社歴の長さ
- 地域での施工実績数
- 類似案件の調査経験
- 調査機器と技術力
- 最新の調査機器の保有状況
- 技術研修の実施状況
- 調査報告書の品質
- 保証制度の有無
- 地盤保証制度への加入
- 万が一の際の補償内容
- NPO住宅地盤品質協会などの第三者機関との連携
地盤調査の不正を防ぐポイント
地盤調査の不正を防ぐためには、以下のような対策が有効です。
- 複数の調査会社から見積もりを取り、内容を比較する
- 調査立会いを行い、実際の調査過程を確認する
- 調査報告書の内容を専門家(構造設計者など)に確認してもらう
- 周辺地域の地盤情報と比較し、極端な差異がないか確認する
地盤調査結果の第三者評価
特に重要な建築物では、調査結果の第三者評価を受けることも検討すべきです。第三者評価機関としては、以下のような組織があります。
- NPO住宅地盤品質協会
- 日本建築センター
- 地盤工学会
信頼性の高い地盤調査会社を選定し、適切な調査を実施することで、将来的な建物の安全性を確保するとともに、不必要な地盤改良工事によるコスト増加も防ぐことができます。
地盤調査のコストパフォーマンスと経済性
地盤調査は建築プロジェクトにおいて追加コストとなりますが、適切な調査を行うことで長期的には大きなコスト削減につながります。ここでは、地盤調査の経済的側面について解説します。
地盤調査の費用相場
調査方法によって費用は大きく異なります。
| 調査方法 | 費用相場(一般的な戸建住宅の場合) | 調査期間 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| SWS試験 | 5〜10万円 | 半日程度 | 最も一般的な調査方法 |
| ボーリング調査 | 15〜30万円/1箇所 | 1〜3日 | 精度が高く詳細なデータが得られる |
| 平板載荷試験 | 10〜20万円 | 1日程度 | 実際の荷重に対する沈下量を測定 |
地盤調査を省略するリスク
地盤調査を省略したり、簡易的な調査で済ませたりすることで、以下のようなリスクが生じます。
- 不適切な基礎設計による建物の損傷
- 不同沈下による壁や床のひび割れ
- 建具の開閉不良
- 配管の破損
- 事後的な補修・補強工事のコスト
- 建物完成後の地盤補強は通常の5〜10倍のコストがかかる
- 居住者の一時退去が必要になる場合もある
- 資産価値の低下
- 地盤に起因する問題は不動産価値を大きく下げる
- 売却時の瑕疵担保責任問題
コストパフォーマンスを高める方法
地盤調査のコストパフォーマンスを高めるためには。
- 適切な調査方法の選択
- 建物規模や地域の地盤特性に応じた調査方法を選ぶ
- 必要に応じて複数の調査方法を組み合わせる
- 調査結果の有効活用
- 過剰な地盤改良を避け、必要十分な対策を講じる
- 基礎形式の最適化による構造コストの削減
- 地盤保証制度の活用
- 地盤調査と地盤改良をセットにした保証制度を活用
- 将来的なリスクに対する保険としての価値
適切な地盤調査は、短期的には費用がかかりますが、長期的には建物の安全性確保とライフサイクルコストの削減に大きく貢献します。特に日本のような地震国では、地盤調査への投資は建物の耐震性向上にも直結する重要な要素です。
地盤調査・地盤改良の費用相場と選び方(建設プラザ)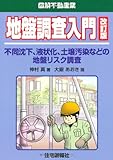
地盤調査入門 改訂版―不同沈下、液状化、土壌汚染などの地盤リスク調査 (図解不動産業)

