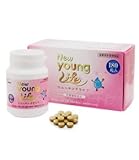ヤング率の一覧と材料特性
ヤング率(縦弾性係数)は、建築材料がどれだけ変形しにくいかを表す重要な指標です。数値が大きいほど剛性が高く、力を加えても変形量が小さい材料となります。建築事業者にとっては、構造設計や材料選定において必須の知識であり、柱や梁の設計、たわみの計算などに直接関わる数値です。
参考)https://www.toishi.info/metal/young_list.html
ヤング率は応力とひずみの比例係数として定義され、フックの法則「σ(応力)=E(ヤング率)×ε(ひずみ)」の関係式で表されます。ただし、ヤング率が高いことと材料の強度が高いことは別の概念であり、混同しないよう注意が必要です。剛性は変形量の小ささを示すのに対し、強度は材料が破壊されずに耐えられる力の大きさを示します。
参考)鋼材のヤング係数|ヤング係数とは何かと合わせてわかりやすく解…
ヤング率の高い金属材料
建築で使用される金属材料の中で、最もヤング率が高いのは鋼材です。一般構造用鋼材(SS材)、機械構造用炭素鋼(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)など種類によって強度は異なりますが、ヤング率はいずれも約205GPa(205,000N/mm²)とほぼ一定の値を示します。これは鉄鋼材料の特徴で、成分や熱処理によって強度は大きく変わりますが、剛性はほとんど変化しません。
参考)ヤング率が大きいとは?1分でわかる意味、かたさとの関係、材料
ステンレス鋼のヤング率は鋼種により若干異なり、マルテンサイト系(SUS410)とフェライト系(SUS405、SUS430)は約200GPa、オーステナイト系(SUS304)は約197GPaとなっています。析出硬化型ステンレス(SUS631)は204GPaで、一般鋼材に近い値を示します。
参考)縦弾性係数(ヤング率)一覧、横弾性係数、ポアソン比との関係
アルミニウム合金のヤング率は約69~74GPaで、鋼材の約3分の1程度です。純アルミニウム(A1100)は69GPa、ジュラルミン(A2017)も69GPa、超ジュラルミン(A2024)は74GPa、超々ジュラルミン(A7075)は72GPaとなっており、合金化による強度向上があっても剛性は大きく変わりません。軽量でありながら一定の剛性を持つため、建築の軽量化が求められる部位に適しています。
参考)ヤング係数を求める時のポイント3つ|大きさによる特徴も紹介!…
銅系材料では、無酸素銅(C1020)とタフピッチ銅(C1100)が117GPa、黄銅系は約103~110GPa、リン青銅(C5212)は110GPa、ベリリウム銅(C1720)は130GPaとなっています。チタン合金は工業用純チタンで106GPa、6Al-4V合金で109GPaと、アルミより高く鋼より低い中間的な値です。
💡 意外な事実:高価な合金鋼でも安価な軟鋼でも、ヤング率はほぼ同じ値を示します。材料選定時には、剛性だけでなく強度や耐食性など複合的に判断することが重要です。
ヤング率のコンクリート特性
コンクリートのヤング率は金属材料と異なり、一定値ではなく設計基準強度と単位体積重量によって変化します。計算式は「Ec=3.35×10⁴×(γ/24)²×(Fc/60)^(1/3)」で表され、γは単位体積重量(kN/m³)、Fcは設計基準強度(N/mm²)を示します。
参考)ヤング係数とコンクリートの関係。計算方法を紹介
一般的な普通コンクリート(γ=23kN/m³、Fc=24N/mm²)の場合、ヤング率は約22,600N/mm²(22.6GPa)となります。これは鋼材の約10分の1程度の値で、木材より高く金属よりは低い中間的な位置づけです。設計基準強度Fcが大きいほどヤング率も大きくなる特性があり、高強度コンクリートの開発により、将来的には鋼材に匹敵する剛性を持つ可能性も研究されています。
鉄筋コンクリート構造では、鉄筋のヤング率が2.05×10⁵N/mm²、コンクリートのヤング率が設計基準強度に応じて変化するため、両者のヤング率比を考慮した構造計算が必要です。このヤング率の違いにより、圧縮力は主にコンクリートが、引張力は主に鉄筋が負担する複合構造が成立します。
参考)https://www.structure.jp/databook/data108.htm
プロテリアル社の解説記事では、鋼材とコンクリートのヤング係数の詳細な比較と建築構造での活用方法が紹介されています
ヤング率の木材とその他材料
木材のヤング率は樹種によって大きく異なり、一般的に7,000~12,000N/mm²(7~12GPa)の範囲です。スギ集成材は約7GPa、ヒノキは約9~10GPa程度とされ、金属材料と比較すると大幅に低い値となっています。木材の特徴は繊維方向と直角方向でヤング率が大きく異なる異方性を持つことで、繊維方向の剛性は高いものの、直角方向では大幅に低下します。
参考)https://www.eng.nipponsteel.com/files_publish/page/76/vol04_10.pdf
木材の詳細データとして、ツガは0.51(気乾比重)でヤング率0.16(繊維方向)、トドマツは0.42(気乾比重)でヤング率0.14、ベイスギは0.37でヤング率0.08と、樹種ごとに特性が異なります。建築構造では、木材と鋼材を組み合わせた木・鋼ハイブリッド構造が開発されており、両材料のヤング率比を考慮した等価断面積比に応じて軸力を分担させる設計が行われています。
参考)ヤング率
樹脂材料のヤング率は非常に低く、ポリエチレンが96~1,240MPa(0.096~1.24GPa)、ポリプロピレンが1,100~1,550MPa(1.1~1.55GPa)、ナイロン6が2,600MPa(2.6GPa)程度です。ガラス繊維入りのエンジニアリングプラスチックでは、ガラス繊維入りナイロン66が10,000MPa(10GPa)と高い値を示しますが、それでも金属材料には及びません。
セラミックス材料は金属を大きく上回る剛性を持ち、アルミナ(Al₂O₃)のヤング率は約360~390GPaと鋼材の約2倍に達します。この極めて高い剛性は、セラミックスが強いイオン結合や共有結合で構成されているためで、半導体製造装置や精密工作機械など、マイクロメートル単位の寸法安定性が求められる用途で活用されています。
参考)ヤング率一覧|金属・樹脂・セラミックスの数値を徹底解説
| 材料分類 | 具体例 | ヤング率(GPa) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 鋼材 | SS400、SUS304 | 197~206 | 高剛性、成分・熱処理で強度変化 |
| アルミ合金 | ジュラルミン | 69~74 | 軽量、鋼の約1/3 |
| コンクリート | 普通コンクリート | 約22.6 | 強度依存、計算式で算出 |
| 木材 | スギ、ヒノキ | 7~12 | 樹種・繊維方向で変化 |
| セラミックス | アルミナ | 360~390 | 超高剛性、鋼の約2倍 |
ヤング率の計算方法と応力・ひずみ関係
ヤング率は応力σとひずみεから「E(ヤング率)=σ(応力)÷ε(ひずみ)」の式で求められます。応力は単位面積あたりに作用する力で、「σ=F(力)÷A(断面積)」で計算され、単位はN/mm²またはMPaです。ひずみは変形の程度を表す無次元量で、「ε=ΔL(変形量)÷L₀(元の長さ)」で求められます。
フックの法則が成立する弾性域では、応力とひずみは比例関係にあり、その比例定数がヤング率です。材料に力を加えていくと、初めは弾性域で直線的に変形し、力を除くと元の形状に戻ります。しかし、ある限界(降伏点)を超えると塑性域に入り、力を除いても変形が残るようになります。
応力-ひずみ線図(応力-ひずみ曲線)は、材料に力を加えたときの応力とひずみの関係を示すグラフで、材料の機械的性質を理解する上で重要です。比例限度までは直線関係が保たれフックの法則が成立しますが、降伏点を超えると非線形となり、最終的には破断に至ります。
実務では、材料試験でひずみを測定し、既知の応力からヤング率を算出します。コンクリートの場合、ワイヤーストレインゲージを供試体に貼付し、圧縮強度試験を行うことでヤング率を測定します。ただし、建築設計では材料ごとに標準値が定められているため、毎回測定する必要はなく、基準値を使用することが一般的です。
参考)コンクリートの物性値一覧(単位体積重量、ヤング係数、ポアソン…
TEC-NOTE の材料定数一覧表では、各種材料の縦弾性係数、横弾性係数、ポアソン比の詳細データと計算式の関係が体系的にまとめられています
ヤング率の単位換算と実務での表記
ヤング率の単位には「N/mm²」「MPa(メガパスカル)」「GPa(ギガパスカル)」などがあり、建築分野では「N/mm²」が最も多く使用されます。これらの単位は「1N/mm²=1MPa」の関係にあり、単位換算しても数値は変わりません。
参考)ヤング係数の求め方&コンクリートや鋼材のヤング係数一覧!単位…
GPaへの換算は「1GPa=1,000MPa=1,000N/mm²」となり、鋼材のヤング率205,000N/mm²は205,000MPaまたは205GPaと表記できます。鋼材のように桁数が大きい材料では、GPa表記が簡潔で読みやすいため好まれます。
参考)ヤング率の単位は?1分でわかる単位、意味、読み方、MPa、k…
古い単位系であるkgf/cm²との換算では、重力加速度が関係します。「1N/mm²=0.102kgf/mm²」の関係があり、1kgf=9.8Nの換算係数を用いて変換します。現在の構造計算ではSI単位系(N、Pa)が標準ですが、古い設計図書ではkgf系が使われている場合があるため、換算方法を理解しておく必要があります。
参考)単位換算方法
単位換算の実例として、鋼材のヤング率を異なる単位で表すと以下のようになります。
- 205,000N/mm²
- 205,000MPa
- 205GPa
- 約20,900kgf/mm²
解析ソフトを使用する際には、入力する材料定数の単位系を統一することが重要です。たとえば、ヤング率をMPaで入力する場合、応力や荷重もMPa系(N、mm単位)で統一しないと、計算結果が大きく誤る原因となります。単位の不統一は構造解析での代表的なエラー要因のため、設計段階で単位系を明確に定めることが推奨されます。
参考)解析前に知っておきたい材料定数と単位系の関りについて
D-MONO WEBの解説記事では、材料定数と単位系の関係について、構造解析における実務上の注意点が詳しく説明されています
ヤング率と剛性・強度の違いを活用した材料選定
建築設計において、ヤング率(剛性)と強度を混同すると適切な材料選定ができません。剛性は「変形のしにくさ」を示すのに対し、強度は「破壊されにくさ」を表す別の概念です。たとえば糸は引張強度が非常に高いにもかかわらず、剛性は極めて低く簡単に曲がります。
参考)今さら聞けない剛性率まとめ~計算方法・構造計算・素材情報一覧…
剛性が重要となる設計例として、精密加工機械や工作機械があります。これらの設備では加工精度を保つため、工具や保持機構に高い剛性が必要で、変形量を最小限に抑える必要があります。建築でも、たわみ制限が厳しい長スパン梁や、振動を抑えたい床構造では、高いヤング率を持つ材料の選定が重要です。
参考)ヤング係数とは?意味・単位・公式をわかりやすく解説しよう!|…
一方、剛性が高すぎる材料は力の吸収能力が低く、衝撃や地震力が直接伝わるデメリットもあります。免震装置や防振構造では、あえてヤング率の低い材料(ゴム、一部の樹脂)を使用し、エネルギーを吸収する設計が採用されます。このように、用途に応じて剛性と強度のバランスを考慮した材料選定が求められます。
耐震設計では、鉄筋コンクリート造(RC造)と鉄骨造(S造)の選択において、ヤング率の違いが構造挙動に影響します。鉄骨造は高いヤング率により剛性が高く変形しにくい反面、適切な靱性確保が必要です。RC造はコンクリートのヤング率が相対的に低く、ある程度の変形を許容しながらエネルギーを吸収する特性があります。
💡 独自視点:ヤング率の異なる材料を組み合わせたハイブリッド構造が注目されています。木材と鋼材を組み合わせることで、それぞれのヤング率に応じた荷重分担が可能となり、コスト削減と環境配慮を両立した構造システムが実現しています。
建築コスト最適化の観点では、ヤング率がほぼ同じ鋼材において、高価な特殊鋼を剛性確保のために選ぶ必要はありません。剛性が目的であれば安価な一般構造用鋼でも同等の性能が得られるため、強度や耐食性など他の要求性能に応じて材料を選定すべきです。このように、ヤング率の特性を正しく理解することで、過剰品質を避けた合理的な材料選定が可能になります。
21ジャンプストリート